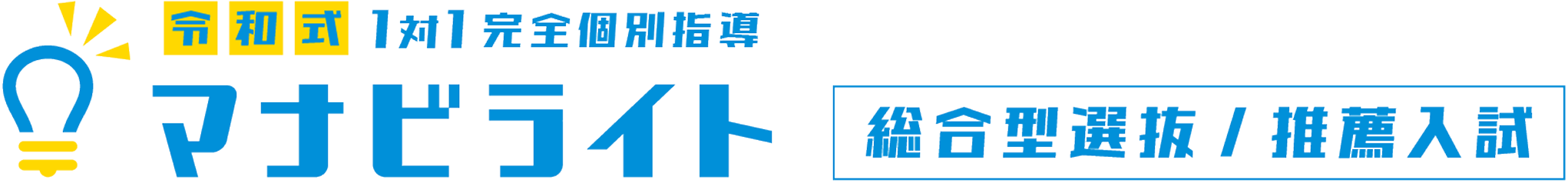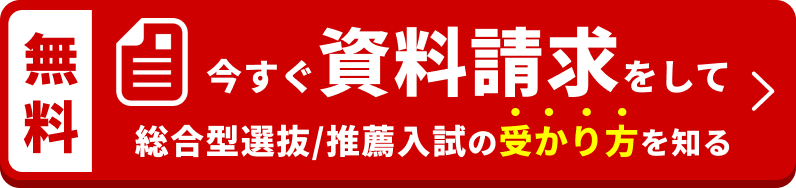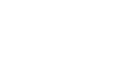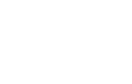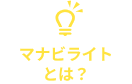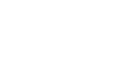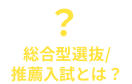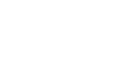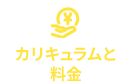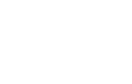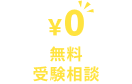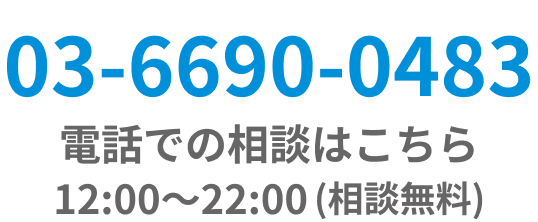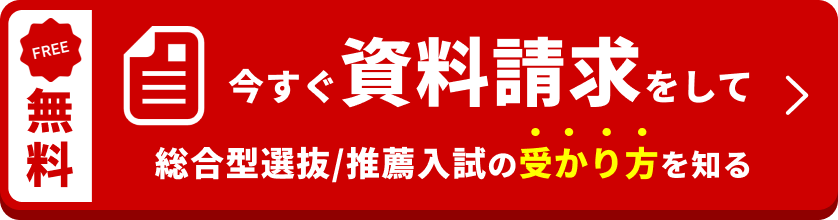いま改めて知っておきたい「推薦入試(学校推薦型選抜)」の基礎知識
大学受験における「推薦入試」は、かつての呼び名であり、2021年度からは正式に「学校推薦型選抜」として制度名称が改められました。とはいえ、高校現場や保護者のあいだでは今でも「推薦入試」という言葉の方がなじみ深く、多くの受験生や保護者がこの制度に注目しています。
文部科学省の発表によれば、現在私立大学の約40%以上の入学者が推薦入試を経て進学しており、国公立大学でも推薦枠の拡大が続いています。かつては「成績優秀者向け」「特別な制度」といった印象が強かった推薦入試ですが、いまや広く一般の受験生に開かれた選抜方法のひとつとなっています。
本記事では、2026年度入試に向けて推薦入試(学校推薦型選抜)の制度概要から出願条件、合格のための対策、さらには合格後の注意点まで、保護者の方が知っておくべきポイントを網羅的に解説していきます。
制度の理解だけでなく、「自分にとってこの選抜方式は向いているのか?」という判断の一助にもなるはずです。
推薦入試は「早期合格の近道」になる一方で、「選抜されるまでの準備や戦略」が非常に重要な制度でもあります。今からできる準備や進路選択のヒントも交えながら、総合型選抜/推薦入試対策のプロ集団であるマナビライトが持つ最新ノウハウに基づいて丁寧にご案内していきます。

推薦入試(学校推薦型選抜)制度の全体像
推薦入試(学校推薦型選抜)とは?他選抜方式との違い
推薦入試は、現在の正式名称で「学校推薦型選抜」と呼ばれ、2021年度入試からの大学入学共通テスト導入に伴って制度が整理・再定義されました。もともと「推薦入試」として広く知られていた制度ですが、現在では以下の3つの選抜方式のうちのひとつとして扱われます。
- 学校推薦型選抜(旧:推薦入試)
- 総合型選抜(旧:AO入試)
- 一般選抜(旧:一般入試)
| 項目 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | 一般選抜 |
|---|---|---|---|
| 推薦の有無 | 高校からの推薦が必要 | 推薦不要 | 推薦不要 |
| 主な評価材料 | 評定平均・書類・面接 | 活動実績・志望理由書・面談 | 学力試験(共通テストなど) |
| 出願時期 | 高3秋〜初冬 | 高3夏〜秋 | 高3冬〜 |
| 専願・併願 | 専願が多い | 併願可が多い | 併願可 |
このように学校推薦型選抜は一般選抜とは評価軸が大きく異なります。
総合型選抜は大学・学部によって同様の評価材料を採用している大学も多いため、「高校からの推薦が必要かどうか」が大きな違いであると言えます。
また学校推薦型選抜の中でも2種類の選抜方式があるため、評価材料等については更に細かく理解する必要があります。
指定校推薦と公募推薦の違い
学校推薦型選抜の特徴は、高校からの推薦を受けて出願する点にあります。
つまり、単なる本人の意思や成績だけではなく、高校における学習状況・生活態度・出席状況などが重要な判断材料になるということです。
これは、たとえば「自己推薦」とも言える総合型選抜や、「学力試験の得点」が重視される一般選抜とは大きく異なります。
指定校推薦
大学が特定の高校に対して推薦枠をあらかじめ提示し、その枠内で校内選考を通過した生徒のみが出願できる制度です。
競争率が比較的低く、合格率も高い一方で、出願後の辞退は基本的に認められない「専願制」となることがほとんどです。
【特徴】
- 高校が推薦できる人数に制限がある
- 出願には校内選考が必須
- 合格後の進路変更ができない(専願)
- 学力試験は課されないことが多い
この方式は「実質的な内定」に近い制度とされ、早期に進路を確定したい生徒にとっては大きな安心材料となります。
反面、推薦枠の有無や条件は高校ごとに異なるため、早期の情報収集が不可欠です。
公募推薦
大学が全国の高校生を対象に出願を受け付け、一定の条件(評定平均・志望理由・活動実績など)を満たす受験生を推薦入試として選抜する方式です。こちらは指定校と異なり、広く門戸が開かれている分、選抜はやや競争的になります。
【特徴】
- 高校に指定されていない生徒でも出願可能
- 評定平均や書類審査が基準になる
- 一部大学では専願ではなく併願可能
- 面接・小論文・学力試験などを課す場合も多い
公募推薦は、高校での学びの成果を大学が独自の視点で評価する制度でもあります。
そのため、評定平均だけでなく「どのような活動をしてきたか」「どのような志望理由を持っているか」といった要素も重要視される傾向があります。
| 項目 | 指定校推薦 | 公募推薦 | 総合型選抜 |
|---|---|---|---|
| 推薦の有無 | 高校が推薦 | 高校が推薦 | 推薦不要(自己推薦) |
| 評価材料 | 評定平均・書類・面接(学力試験なしが多い) | 評定平均+面接・小論文・活動実績(学力試験ありも) | 活動実績・志望理由・面談・課題など |
| 学力試験 | ほぼなし | 大学により課す場合あり(共通テストや独自試験) | 一般に課さないが大学により課す場合も |
| 評定条件 | 明確な基準あり (例:評定平均4.0以上) | 基準あり (例:3.5以上など) | 基準なし or 緩め(大学独自) |
公募推薦では、評定平均に加えて志望理由書や活動実績が問われるケースが多く、評価方法が総合型選抜と同様のものになる大学もあります。
ただし、出願には高校からの推薦状が必要であり、評定の基準が明確に設けられている点で、総合型選抜とは制度的に異なります
推薦入試(学校推薦型選抜)
出願条件と合格判定基準
評定平均とは?算出方法と大学ごとの基準例
推薦入試(学校推薦型選抜)では、出願の前提として「評定平均(内申点)」の基準を満たすことが求められます。
総合型選抜に、出願資格に評定基準がない方式でも、採点時に間接的に評定が考慮される傾向があります。
評定平均とは、高校1年から3年の成績を5段階で評価し、それを教科ごとの単位数に応じて加重平均したものです。
評定平均の計算方法(文部科学省基準)
たとえば、主要5教科(国・数・英・理・社)および副教科(音楽・美術・保健体育など)すべてを含む「全科目の加重平均値」で計算します。
【例】英語5(3単位)、国語4(2単位)、数学3(4単位)…などを加重して合計
⇒ 各教科の「成績 × 単位数」を合計し、総単位数で割る
【ある受験生の2年次成績】
| 科目名 | 評定 | 単位数 | 評定×単位 |
|---|---|---|---|
| 現代文 | 4 | 2 | 8 |
| 数学Ⅱ | 5 | 4 | 20 |
| 英語表現 | 3 | 2 | 6 |
| 化学 | 4 | 3 | 12 |
| 世界史 | 5 | 3 | 15 |
| 保健体育 | 4 | 2 | 8 |
| 音楽 | 5 | 2 | 10 |
| 家庭基礎 | 3 | 2 | 6 |
| 合計 | ― | 20単位 | 85点 |
評定平均 = 評定×単位の合計 ÷ 総単位数
= 85 ÷ 20 = 4.25
この生徒の2年次の評定平均は「4.25」となります。
実際は、高1〜高3の全学年全科目の平均で算出します(高3は1学期または前期分まで)
大学ごとの評定平均の基準例
| 大学名 | 学部名 | 指定校推薦(評定平均) | 公募推薦(評定平均) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 政治経済学部 | 4.0以上(英・国4.0+他1科4.5以上) | 実施なし | 公募推薦枠なし(指定校のみ) |
| 文学部 | 4.0以上 | 3.5以上 | 学科ごとに条件の細かい違いあり | |
| 商学部 | 4.0以上 | 4.2以上 | 商学系の公募は高基準・資格加点あり | |
| 青山学院大学 | 文学部(英米文学科) | 4.0以上 | 4.0以上 | 英検準1級などを求めるケースあり |
| 教育人間科学部 | 3.8以上 | 3.8以上 | 評定基準は公募と同水準 | |
| 経済学部 | 4.0以上 | 3.8以上 | 公募は小論文・面接あり | |
| 同志社大学 | 法学部 | 4.0以上 | 3.8以上 | 両方式で指定の評定あり |
| 商学部 | 4.0以上 | 3.8以上 | 英検加点のあるケースも | |
| グローバル地域文化学部 | 4.0以上 | 3.9以上 | 語学力重視傾向あり | |
| 立命館大学 | 法学部 | 4.0以上 | 3.7以上 | 小論文・プレゼン課す大学が多い |
| 経営学部 | 4.0以上 | 3.8以上 | 公募推薦は書類重視+口頭試問型 | |
| 国際関係学部 | 4.0以上 | 3.8以上 | 英語資格スコア併用条件あり |
※マナビライト調べ
・「指定校推薦」の評定基準は高校ごとに異なり、あくまで目安です。
・「公募推薦」は各大学の募集要項により、評定平均以外の条件(英検・小論文・面接等)が課されることがあります。
・最新の情報は、各大学のホームページまたは高校経由の推薦枠資料で必ず確認をお願いします。
必要書類と選考プロセス:面接・小論文・外部検定
推薦入試では、以下のような書類を用いた選考が一般的です
基本的な提出書類
- 調査書(評定平均・出席・活動履歴など)
- 推薦書(高校の進路指導部・担任が作成)
- 志望理由書(なぜその大学・学部を志望するか)
- 自己推薦書・活動報告書(部活・生徒会・地域活動・ボランティアなど)
これらは単なる「事実の記録」ではなく、人物評価や大学とのマッチ度を測る材料になります。
特に志望理由書・活動報告書は、書き方次第で合否を大きく分けるため、プロによる添削サポートが有効です。
面接・小論文などの選考内容
大学によって選考内容は異なりますが、主に以下の形式があります。
| 選考内容 | 主なポイント |
|---|---|
| 面接 | 個別・集団ともにあり。 志望理由・将来のビジョン・大学&学部への理解度などを問われる。 |
| 小論文 | 社会課題や学部に関係するテーマが中心。論理的思考と文章構成が問われる。 |
| プレゼン型試験 | 一部大学ではプレゼン・ポートフォリオ提出などを求めるケースもあり。 |
| 共通テスト or 学力試験 | 国公立では共通テストの得点を一部加味する推薦入試も存在。 |
大学が何を重視しているかは、「募集要項」「入試ガイド」「過去問題」などをチェックすることが一般的です。
人気大学では、小論文やプレゼンで「独自性」や「社会性」を問う傾向も強まっているため、単なる丸暗記型の対策だけでは合格を掴み取ることは出来ません。
また大学側が掲げる「アドミッションポリシー」に沿った対策が必要となるため、独学や学校での対策は非常に難易度が高いと言えます。
塾選びをする際には推薦入試や総合型選抜の対策に実績がある塾を選ぶことがポイントとなります。
単に有名大学への合格実績が多くあることは、推薦入試や総合型選抜での合格率が高いこととは関係がありません。
評定は「出願の条件」
合否は「総合評価」で決まる
多くの受験生が「自分の評定じゃ無理かも…」と不安になりますが、実際には評定は出願のための“最低条件”にすぎず、合否は書類・面接・論文など多面的な評価で決まるのが実態です。
逆に、評定が高くても志望理由が曖昧だったり、面接で印象が悪ければ合格できないこともあります。
受験生は「数字」だけで判断するのではなく、「自分の強みがどのように評価される制度なのか」を深く考える視点が大切です。
推薦入試(学校推薦型選抜)のスケジュールと合格に向けて必要な準備
推薦入試(学校推薦型選抜)は、一般入試よりも早い時期に出願・選考が行われます。
特に「指定校推薦」は高校内の選考が前提となるため、夏前から準備を始めていないと間に合わないケースもあります。
ここでは、推薦入試の一般的なスケジュールと、どう対策すべきかを時系列で解説します。
推薦入試の一般的なスケジュール
| 時期 | 主な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月〜6月 | 校内推薦の基準発表・面談開始 | 各高校で推薦枠の概要を説明。評定の条件確認が必須 |
| 7月〜9月 | 校内選考(指定校推薦)/大学要項公開(公募推薦) | 指定校は校内締切が9月前後、公募は募集要項・課題発表も |
| 10月中旬〜11月中旬 | 出願・書類提出 | 各大学で推薦入試の出願受付期間が異なる(特に公募推薦) |
| 11月中旬〜12月上旬 | 試験(面接・小論文など) | 曜日指定や複数日程もあるため要注意 |
| 12月中旬〜下旬 | 合格発表 | 私立大学では年内発表が多い。国公立は翌年1〜2月も |
※大学・学部によって若干の前後があります。必ず「募集要項」で確認してください。
推薦入試に向けた準備
評定平均の確認と対策
推薦入試では出願条件として評定平均(内申点)が求められるため、まず「出願可能な大学・学部の基準」を調べ、現在の成績と照らし合わせることが第一歩です。
- 高校から通知される評定一覧表を確認
- 希望大学の必要評定と照合(例:4.0以上など)
- 定期テスト対策
- 副教科(美術・体育など)も成績に含まれる点に注意
出願書類の準備
推薦入試で必要となる「志望理由書」や「活動報告書」は、単なる提出書類ではなく、大学とのマッチングを示す重要な評価資料です。
プロによる「誰にでも書ける内容になっていないか?」という視点でのチェックが必要です。
- 志望動機が「学部の理念」に沿っているか確認
- 活動内容が具体的か(部活・生徒会・ボランティアなど)
- 「過去・現在・未来」の話が網羅出来ているか
推薦入試(学校推薦型選抜)は“早い者勝ち”ではなく“準備した者勝ち”
推薦入試というと「早く決まってお得」というイメージを抱かれがちですが、実際は短期間で多くの準備が必要な選抜方式です。
評定、書類、面接、小論文といった多面的な評価に備えるには、早期から計画的に動くことが合格へのカギです。
推薦入試(学校推薦型選抜)のメリット・デメリットを判断する
推薦入試は、早期に合格できる可能性があり、多くの受験生・保護者にとって魅力的な制度です。しかし、「とりあえず推薦で出せるなら出そう」と考えるのは危険です。制度の特性を理解せずに進むと、進学後のミスマッチや後悔にもつながりかねません。
ここでは、推薦入試の長所と短所を冷静に比較し、「自分に(子どもに)合った制度かどうか」を判断するための視点を解説します。
推薦入試(学校推薦型選抜)の主なメリット
年内に合格が決まる
多くの私立大学では、11月〜12月には合格が発表されます。一般選抜よりも2か月以上早く進路が確定するため、
- 学力試験の不安から早期に解放される
- 共通テストや冬期講習の費用を抑えられる
- 高3後半にやりたい活動に時間を使える
など、心理的・経済的なメリットが得られます。
主に学力以外の力が評価される
推薦入試では、調査書・面接・小論文・活動実績などを通して、学力以外の「人となり」や高校での頑張りが可視化される制度です。
- 部活動、生徒会、探究学習などの継続力が強みになる
- 英検やTOEICなど外部資格が加点される場合も多い
- 指定校推薦であれば、学力試験なしで進学できる学部も
特に、「テストよりも人柄や努力を見てほしい」タイプの生徒には強く合う傾向があります。
学力水準以上の大学を狙える可能性も
指定校推薦は「大学側がその高校を信頼して設ける特別枠」であり、一般選抜に比べて偏差値や倍率の壁が低く設定されるケースがあります。
- 一般では難関でも、推薦枠経由で“合格実績”を出している高校は多数
- 評定平均が安定していれば、“ボーダー突破”ではなく“推薦基準クリア”で勝負できる
これは、一般入試に自信が持てない受験生にとっては戦略的な進学ルートとなり得ます。
推薦入試(学校推薦型選抜)のデメリット
専願が多く、辞退できない(特に指定校)
多くの指定校推薦は「専願制」であり、一度合格すると他の大学を併願できません。
辞退も原則不可で、合格=進学確定です。
- 合格後に気が変わっても進路変更ができない
- 他の可能性を探る余地がなくなるため、慎重な進路選択が必要
※特に進学後のミスマッチ(学部内容・雰囲気・立地など)による退学リスクもゼロではありません。
校内選考の“見えない競争”がある
推薦入試は「出願させてもらえるかどうか」を校内で決める必要があります。
評定だけでなく、生活態度や出席状況、部活動などの“総合評価”で選ばれます。
- 同じ高校内での“密かな競争”に気づかないことも
- 選考が不透明と感じる保護者も多い(→学校との連携が不可欠)
合格後の学習モチベーション低下
「受かったからもう勉強しなくていい」と感じてしまい、入学後に苦労する生徒も少なくありません。
- 特に推薦組は入学後、一般入試組と比較して最初のテストで差を感じやすい
- 進学先のレベルに自分が「相応しいかどうか」の不安を抱くことも
推薦入試(学校推薦型選抜)で“後悔しない”ための確認リスト
推薦入試で志望校合格を目指すことはチャンスも多いですが、一歩間違えると大きな失敗・後悔に繋がりかねません。
以下のチェックリストで、納得度を確認してください。
☑志望理由は本人の言葉で説明できるか
☑入学後にどんな学び・進路を期待しているか明確か
☑評定平均・生活記録など学校への信頼度があるか
☑推薦で決まった場合の“気持ちの切り替え”計画があるか
☑推薦が不合格の場合の次の選択肢も準備済みか
推薦入試(学校推薦型選抜)は“活用すれば強い武器”に!
推薦入試は「楽な道」ではなく、「高校生活を誠実に過ごしてきた人に与えられる戦略的なチャンス」です。
推薦で進学した生徒が「大学生活を前向きにスタートできるかどうか」は、家庭が制度の仕組みを理解し、一緒に考え抜いたかどうかにも左右されます。
こんなあなたは推薦入試(学校推薦型選抜)が向いています
推薦入試は誰にでも平等に向いている制度ではありません。制度のメリットを最大限に活かすには、「自分はこの方式で力を発揮できるタイプなのか?」を知ることが非常に重要です。
ここでは、受験生本人の特性や高校生活での行動パターン、将来に対する意識などから、推薦入試に向いているタイプ/向いていないタイプを見極めるためのチェックポイントを紹介します。
推薦入試(学校推薦型選抜)が「向いている」人の特徴
評定平均が安定している人
推薦入試はまず「出願資格」として評定平均の基準をクリアする必要があります。
この基準は多くの大学で3.5〜4.0以上が目安とされており、日々の授業・課題・提出物を丁寧に取り組んできた人ほど有利です。
☑ 定期テストで平均点以上をキープできている
☑ 提出物や課題の遅れが少ない
☑ 生活面の評価(出席率・素行)に問題がない
面接や志望理由書で「言葉で伝える力」がある人
推薦入試は学力試験よりも「書類+面接」で評価されることが多く、自分の考え・経験・将来やりたい事を明確にし相手に伝える力が必要です。
☑ 志望動機を自分の言葉で説明できる
☑ 面接でも緊張しすぎずに話せるタイプ
☑ 他人のアドバイスを受けながら文章を改善できる
高校生活での取り組みに一貫性がある人
推薦入試は「高校生活で何に取り組んできたか」「大学で何を学びたいのか」「それを将来、何に活かしたいか」が評価の軸になります。3年間の積み重ねがある人ほど有利です。
☑ 部活や委員会、生徒会などを継続して取り組んだ
☑ 探究活動や地域イベントなど学校外の取り組みがある
☑ 評定だけでなく行動面でも表彰・実績がある
勘違いしやすいですが、令和時代の推薦入試や総合型選抜は「一芸入試」ではありません。
好きな事や得意な事を深堀り出来ることが、評価に繋がります。
志望校・志望学部が明確な人
推薦入試は基本的に“専願”が多く、合格したらその大学に進学しなければなりません。途中で気が変わる可能性が低い人ほど向いています。
☑ なぜその大学・学部に進みたいかをはっきり語れる
☑ 学びたい分野や将来の方向性がある程度固まっている
☑ オープンキャンパスやパンフレットなどで情報収集している
推薦に向いているかどうかは「数字」だけでなく「姿勢」で決まる
推薦入試は、単に成績が良ければ合格できる制度ではありません。
むしろ、「普段の姿勢」「志望への本気度」「自分を言葉で表現する力」といった総合的な人間力が問われます。
この章を読んで「自分は推薦に合っていそう」「少し不安かも」と思った方は、次章で紹介するQ&Aでのケース別解説もぜひ参考にしてみてください。
受験生の不安を解消!推薦入試(学校推薦型選抜)Q&A(2026年度版)
推薦入試によくある疑問を“ズバリ”解決!親子で安心できる制度理解を
推薦入試を検討し始めた段階で、多くの受験生や保護者が「評定が足りないとどうなるの?」「もし落ちたらどうすれば…」といった疑問や不安を抱えます。
ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、2026年度入試制度に対応した推薦入試Q&Aをまとめました。
Q1. 評定平均が基準に届いていない場合、推薦は絶対に無理?
🅰 評定が出願条件に満たない場合は、その推薦枠には原則出願できません。大学・学部によっては評定3.5以上、4.0以上などの最低ラインが明示されています。
ただし、
- 高校内での校内選考(指定校)は多少の融通が効くこともある
- 公募推薦であれば、資格(英検など)や活動実績でカバーできる可能性もあり
まずは学校の進路指導室で、推薦枠の条件を具体的に確認することが最優先です。
また、総合型選抜は出願基準に評定を課さない大学・学部も存在するため、狙い目となるケースが増えてきています。
Q2. 推薦入試が不合格だった場合、一般入試には出願できる?
🅰 はい、基本的にはできます。
ただし注意が必要なのは「専願型」の推薦入試です。これに出願する際は、合格したら必ずその大学に進学することが条件です。
- 専願:合格したら他の入試は受けられない
- 併願:合否にかかわらず、他の大学にも出願できる
公募推薦は併願可能な大学も多いですが、「出願時点での併願可否」や「辞退の可否」は大学によって異なります。募集要項を必ず確認しましょう。
Q3. 推薦で落ちたら“推薦に向いていない”ってこと?
🅰 いいえ、そんなことはありません。推薦入試は倍率が低いわけではなく、書類の完成度や面接でのやりとりで結果が変わることもあります。
- 志望理由書に個性や具体性が足りなかった
- 面接で緊張してうまく伝えられなかった
- 評定は高くても活動実績に乏しかった
落ちた理由を分析して一般選抜や別の大学の推薦で挽回することは十分可能です。
Q4. 推薦の面接ってどんなことを聞かれる?対策はどうする?
🅰 面接の内容は大学・学部によって異なりますが、主に以下のようなことが問われます
- なぜこの大学・学部を志望したのか
- 高校生活で頑張ったこと
- 将来どう活かしたいか
- 調査書・志望理由書の内容について深掘りされる
模擬面接を複数回行い、志望動機と将来像を「自分の言葉」で説明できるようにすることが最大の対策です。
Q5. 推薦入試(学校推薦型選抜)で“燃え尽き症候群”になるって本当?
🅰 実際にあります。推薦で早期に進学先が決まり、「その後勉強しなくなってしまった」という例は珍しくありません。
- 推薦合格者の中には、入学後の授業についていけず不安になるケースも
- 一般入試で入った学生と比べて、モチベーション維持が難しくなる場合も
合格後も「入学後に何を学ぶか」を意識し、英語や基礎科目の先取り学習を勧めるとスムーズな大学生活に繋がります。
不安が出てくるのは“本気で考え始めた証拠”
推薦入試は、制度が複雑で「何となく進めていいものではない」からこそ、不安や疑問が出てくるのは当然のことです。
大切なのは、不安を放置せず、「わからないことは調べ、相談し、備える」姿勢です。
注目!2026年度の推薦入試(学校推薦型選抜)最新トレンド
早稲田・慶應・地方国公立…推薦入試が“特別枠”から“戦略枠”へ進化中!
2026年度の推薦入試(学校推薦型選抜)は、制度そのものの大きな変更はありませんが、大学側の運用において明確な“戦略化”が進んでいるのが近年の特徴です。
ここでは、最新の動向を踏まえて「どのような大学・学部がどんな推薦方式を取り入れているか」「何に注目すべきか」をまとめて解説します。
難関私大でも推薦枠が拡大中
以前は「推薦入試=中堅私大中心」と思われがちでしたが、いまや早慶上智、MARCH、関関同立など難関私大でも推薦入試の実施数が年々増加しています。
例:早稲田大学「全国自己推薦型選抜」(実質的な公募推薦)
- 評定平均4.0以上+課外活動や志望理由による評価
- 学部によっては英検準1級以上を必須とするケースも
- 合格倍率は3〜10倍と一定の競争あり
(参考:waseda.jp)
例:明治大学 商学部「公募特別入学試験」
- 評定平均4.2以上
- 書類・面接・小論文を総合評価
- 英語外部検定のスコア提出で加点
(参考:meiji.ac.jp)
難関大学が“学力だけでは測れない人物”を獲得するため、推薦枠を「戦略的な人材獲得手段」として活用する傾向が見られます。
地域枠・医療・教育系推薦は“実質総合型”化の傾向も
国公立大学や医療・教育系の学部では、「地域貢献型推薦」や「学科系統別推薦」などの多様な枠が増加しています。
例:福井大学・山形大学など 地域医療枠
- 地域の高校出身+一定年数の地元勤務を条件に推薦枠を設定
- 面接・志望理由・地域貢献への意欲が重視される
例:教育学部(全国多数)
- 評定平均3.8〜4.0+教育実習経験・ボランティア経験を重視
- 特別支援教育などのコース別推薦もあり
これらの推薦は、学力試験よりも“本人の目的意識”が強く問われる選抜形式に変化してきています。
英語外部検定や資格でのアピールが標準化へ
特に都市部の私立大学では、推薦入試の評価基準として以下のような「スコア型・資格型評価」が明示されることが増えています。
| 評価項目 | 内容・目安 |
|---|---|
| 英検 | 準1級以上で加点 or 出願条件に(早稲田・青学など) |
| TOEFL iBT/IELTS | スコア60~80以上で出願可能(立命館・上智など) |
| ボランティア実績 | 特定分野の推薦で評価材料(教育系など) |
| 探究活動レポート | ポートフォリオ提出を求める大学も増加中 |
共通テストを課さない代わりに、別の“学力的指標”を求める動きが進んでいると言えます。
推薦入試(学校推薦型選抜)が“戦略”で使われる時代に
これまで「指定校推薦=枠があれば出す」「公募推薦=滑り止め」という考え方も多く見られましたが、現在はまったく異なります。
- 難関大学の推薦を狙って計画的に準備する受験生
- 活動実績を武器に、公募推薦一本で複数学部を狙う受験生
- 地域枠や医療推薦を通じて、将来像まで見据えて進学するケース
推薦入試は、「制度を理解し、数値だけでなく中身で勝負できる受験生」が評価される制度に進化しています。
推薦入試(学校推薦型選抜)は“変わらない制度”ではなく“進化する選抜”
2026年度の推薦入試は、制度の枠組みこそ変わらないものの、大学側の運用や評価軸は明らかに高度化・多様化しています。
志望校合格を目指す受験生は、単に「推薦枠があるか」ではなく、
- どの推薦方式を
- どんな評価基準で
- どこまで準備して挑むのか
という視点で進路を戦略的に考えることが重要です。
また、状況に応じて総合型選抜を取り入れる大学・学部が増えていることから、総合型選抜についてもしっかりと正しい知識を付けた上で最適と思われる選択をしていきましょう。
おわりに|チャンスを増やす進路の選択肢としての学校推薦型選抜(推薦入試)
推薦入試は“早く決まる制度”ではなく、“戦略的に活用する制度”です。
推薦入試は、単に合格の早さや倍率の低さを狙うものではありません。
それは、高校3年間の努力や積み重ね、志望への想いを丁寧に見てもらえる、「人物重視の選抜方式」です。
この記事では、推薦入試の制度や種類、出願条件、選考内容、判断のポイント、そして最新の動向までを包括的にご紹介してきました。
受験生が推薦入試について正しく理解し、最適な選択肢かどうかを考えることこそ、最も大切な準備だと私たちは考えています。